SDキャラの進捗と、マヤとローズのお話(過去のSS再録)
2020.11.21
SDキャラ、あと少し~!(…でもない)

ヴァイゼスの残りはララ、レイチェル、リーリエですね。
あとはミルフィーユとリコリスとアツシとジュラード……あと少し……!
今日はあまりブログを書く余裕が無いので、
過去に旧サイトに載せていたマヤとローズのSSを再録しておきます!↓
あ、今日の落書きは妖精マヤとうさこです!

—————————————-
【マヤとローズのお話】
※本編『あなたの幸せを願う』後のお話
俺はまだ多くを知らないから。アリアのことも、君の事も。
『アリアは……』
そう彼女のことを話すマヤは、俺の知らない顔をしていた。
懐かしむようで、悲しむようで、辛そうで、でも時折笑みが零れる彼女の表情。
そんな君の表情、知らない。昔も今も。
でも、少し懐かしい気もする。
忘却の地という特殊な寒さに包まれたここは、日が落ちればさらに寒さを増す。俺は窓の外に見える寒々しい色の空を見ながら、ベッドの上で毛布に包まった。
「ローズ、ちょっといいかな?」
夜もだいぶ更けてきた頃、俺にあてがわれた部屋にそう言ってマヤが訪ねて来る。時間的にそろそろ寝ようかとも思っていたが、散々寝ていたためにあまり眠気は無かったので、俺はマヤの訪問にベッドから立ち上がって彼女を迎えた。
「ごめん、寝てた?」
「いや、起きていたから気にしないでくれ。それよりどうした?」
彼女が魔法で火をつけてくれた暖炉の火がまだ煌々と燃えているため、室内は暖かい。彼女はその温度を廊下に逃がさないために、部屋のドアをしっかりと閉めて中に入る。
「ちょっと様子を見に、ね……ほら、大丈夫かなって」
マヤはそう言って控えめな笑みを見せる。心配性な彼女らしいと、そう思いながら俺は「そうか、ありがとう」と言った。
「体、ホントに大丈夫?」
「ん……自分的にはこれといっておかしいと思うところは無いぞ」
まだ見慣れない自分の紅い髪を弄りながら、俺は心配そうに眉を顰める彼女にそう言葉を返す。
「そう、ならいいけど……でもね、何か気になることがあったら直ぐアタシに言ってね?」
まだ不安げな顔をする彼女に、俺は「本当に大丈夫だから」と笑って答える。
「マヤは心配性だな、本当に」
そう何気なく呟くと、マヤは何故か自嘲気味に笑った。
「自覚あるわ、それ。……だって怖いの。だから、心配しちゃうのよ」
「怖い?」
「……」
俺の疑問に、マヤは何も答えない。そのかわり彼女は近くの椅子に腰掛け、「まだ寝ないなら少し話しでもしよっか」と言った。
「話し?」
「うん。改めてもっとローズのこと、知りたいなって思ったから。だからマヤちゃんからローズにインタビュー! ……どうよ」
いつもの彼女らしく明るくおどけた様子でそう言うマヤに、俺は苦笑いと共に「なんだそれは」と返す。
「いいじゃん、アタシはもっとあなたのこと知りたいのよ」
「前もそう言っていたな。あの時、だいぶ俺のこと話した気がしたんだが……」
ベッドに腰掛けながら、俺は彼女と向き合う。マヤは「いいじゃない」と笑った。
「はいはい、んじゃ早速しつもーん」
「あ、待ってくれ」
「ん?」
俺がマヤの言葉を遮ると、彼女は不思議そうな顔で「なによぉ」と小首を傾げる。
「それなら俺もお前にいろいろ聞きたいんだが……」
「アタシぃ?」
俺の言葉に驚いたのか、マヤは目を丸くして「なんでいきなり」と言う。俺は少し困って、頬を掻きながら答えた。
「いや……俺もそんなにお前のことを知らないなと、そう思って……」
「そう? アタシのことなんてこの前洗い浚い喋った気がするけどぉ?」
「いや、それを聞いてそう思ったんだ。俺はお前のこと、何も知らなかったんだなぁって。だからその、聞きたいと……」
それだけじゃない。過去を語る彼女の姿が俺の知らない”マヤ”で、なんだかそれがとても印象的だった。
「なぁに、それ。なんかそう真面目な顔で聞かれると恥ずかしいからやめてよ」
「そ、そうか?」
マヤがそう言って少し照れたように笑うので、俺も思わず恥ずかしくなってしまう。
「ま、いいや。いいよ、ローズがアタシに何か聞きたいことがあるなら聞いてよ。知りたいならバストサイズも答えてあげるわよん」
「そ、そういうのはいい!」
「あはは、ローズってば照れてかわいー」
マヤがおかしそうに笑うのを、俺は少し恨めしそうに見る。
「むっ……あまりそうやってからかわれるのは慣れてないんだ……」
「ごめんごめん、冗談よ。で、なにを聞きたい?」
マヤのその言葉に、俺は改めて考える。
聞きたいことは色々あるんだ。たとえばアリアのこと。でも今はまだ彼女にそれを面と向かって聞く勇気が無かった。
「……お前は強いよな。心も体も、強い。どうしてお前はそう強くいられるんだ?」
「え?」
悩んだ末に出た言葉は、唐突なもの。
「強い? ……アタシが?」
「いや、そう思ったんだ。だってお前は何年も、辛い記憶を抱えながら明るく生きているから」
「……そう、見える?」
マヤは表情を少し暗くさせ、ひどく真剣な声音でそう呟く。
「俺はお前の過去を聞いて、そして今のお前を見てそう思ったんだ。……違うのか?」
俺の問いに、マヤははっきりと「違うわ」と返す。
「アタシは強くないわよ。……弱いから、そう見せてるだけよ」
ひどく大人びた彼女の表情。やはりそれも、俺のあまり知らないマヤの表情だった。
「……」
「あら、どうしたのローズ。そんな呆けた顔して」
彼女はまた普段どおりの顔で、俺の顔を不思議そうに覗きこむ。いや、もしかしたら先程の俺の知らない彼女の表情が素で、俺やユーリたちに見せる明るい彼女が繕った彼女の姿な気がする。
「……いや、なんでもないさ」
「そう? 変なローズ」
自分の知らない彼女の姿を意識し始めたら、それが凄く気になるようになってしまった。
「……そうね……昔、同じような事を言われたことがあったわ」
「ん?」
マヤは青い瞳を細め、何かを懐かしむように口を開く。
「彼女も同じ事言ってた」
「彼女?」
「そ。……アリアもアタシを強いって、そう言ってた」
「あぁ……」
彼女の方からアリアの話が出るとは思わず、俺は少し驚きながら言葉を漏らす。
「そうか。アリアも、お前を『強い』と言っていたのか」
確認するように、俺は呟く。マヤは少し寂しげな笑顔で「うん」と頷いた。
「彼女、勘違いしてたから。自分は何も出来ないって。そんなことないのに、そう言って……それでアタシのこと、羨ましいって言ってたの」
「羨ましい……」
「うん。彼女の目には、きっとアタシはバリバリ戦えて一人で生きてける強い女に映ったんだろうね。……本当は、全然そんなことないのにさ」
「……」
澄んだ青の瞳がどこか遠くを見つめる。きっとここではない、遠い過去を見ているんだろう。
「本当は、当時のアタシはアリアに支えられていたんだよ。彼女が心の支えで……彼女に出会ってしまったから、もう彼女無しじゃ生きられなくなってしまった……」
マヤの告白は辛いし、怖い。
彼女はアリアに依存し、そして最悪の形で彼女を失い、その結果アーリィが生まれた。その告白を聞いた後、正直俺は今後も今までと同じようにマヤやアーリィと接していけるのかと心配と不安を抱いた。それでも結果俺は今までどおりにマヤたちと接している。いや、そういう風に見えるし、俺たちは互いにそれを装っているん だと思う。だけど一度深いところまで聞いてしまったことは事実。今の平常は最初の頃とは明らかに違う凄く脆いものだと、そんな気がするからマヤの告白は怖かった。
彼女の告白を聞けば聞くほど、今までのような俺たちではいられなくなる。でも、それを覚悟してでも彼女の告白を聞くべきだとも、俺は思った。それが彼女を知ることになるのだから。
「アタシの方こそ彼女が羨ましかったかもしれない。彼女のように、心から笑って生きられたら……なんて、それもアタシの妄想かもね」
やはりアリアのことを語るマヤは、俺の知らない顔をした彼女だった。だけど……
「妄想?」
「アタシこそ、彼女のこと何もわかってなかったのかもなって思って。……彼女のこと、本当は何も理解してなかったのかも知れない」
「……」
目を伏せる彼女が、とても脆く見える。悲しい痛みを見せる彼女に、ひどく胸が痛んだ。
「アーリィを造る時、それを凄く感じたの。基本となる人格をコアに刻むために、アタシは彼女の人格を作ろうとした。でも彼女の思考を辿ろうとしても、全然駄目だった。やっぱり彼女は他人で、どんなに理解したつもりでも他人の心を真に理解することなんて出来ないんだって……そう思ってがっかりしたよ」
「……自分自身のことだって理解するのは難しいんだ。なら、他の者のことなど尚更難しいだろう……」
「そうね……そのとおりよ」
溜息を吐き、マヤは小さく俺に笑みを向ける。
「アリアがアタシに憧れていたと同じ理由で、アタシも彼女に憧れていたと思うわ。だから、アタシは彼女を理解出来ていなかったんだと思う」
「お前にとってアリアは、憧れだったのか?」
「憧れでもあり、支えでもあったよ。依存していた……ずっと一人だったから、自分と同じ”異端”だった彼女にアタシは……」
今まで少し俯き加減だったマヤが、突然勢いよく顔を上げる。彼女はいつも俺たちに見せる彼女の笑顔で、俺を見つめた。
「ごめん、なんか途中から随分湿っぽい話しになっちゃったね」
「あ、いや……いいんだ、俺がお前のこと聞きたいって言ったんだし」
互いに気を使った笑顔を向ける。そういことはお互い理解できてしまうのが寂しい。
「……ありがとう、マヤ。少しだけ、お前のことわかった気がするよ」
「そう? なんだかやっぱり面と向かってそう言われるとちょっと恥ずかしいわね」
マヤの照れた笑みに、やはり俺もつられて照れを感じてしまう。でも内心で俺は先程の言葉は嘘だと、そんなことも考えていた。
自分で言った事だ。他人を真に理解することなんて、本当は出来ないだろう。彼女には、俺の知らない部分が永遠にあるんだと思った。そしてそのことが少し寂しいと、そう思った自分がいて少し戸惑う。
「んで、他に何か聞きたいことは?」
「ん、他にか?」
マヤのその言葉で意識を現実に戻す。
「……いや、今はいい」
「そう?」
これ以上は、まだ聞く勇気が無かった。他人に対して少し臆病なのは昔からかわらない。それを考え、自然と自嘲気味な笑いが漏れた。
「なぁに笑ってるのん?」
「あ、なんでもないさ」
「えぇー、怪しいわね」
「はは、すまない」
俺の知っている表情で俺の顔を覗きこむマヤに、安堵を覚える。安心するんだ、やっぱり。今のような笑顔の彼女が、俺の知っている彼女だから。
昔を想う彼女の表情は、凛とした強さと危うい儚さを併せ持つ俺の知らない顔。俺じゃない”誰か”が知る彼女の表情は、見ていて不安になるから怖いんだ。痛々しい彼女のその表情も、それを懐かしいと感じて不安に思う自分も、その両方が怖くて。
「……お前にはそうやってずっと笑っていてほしいよ」
思わず口を付いて出た言葉に、マヤは目を丸くして「なに言ってるのよ」と返す。少し顔が赤くなった彼女に気づいて、俺もかなり恥ずかしくなった。
「す、すまん……」
「……ほんと、変なローズ」
また、彼女が笑う。その屈託の無い笑みに俺も笑顔を返した。
【end】
NEW POSTED
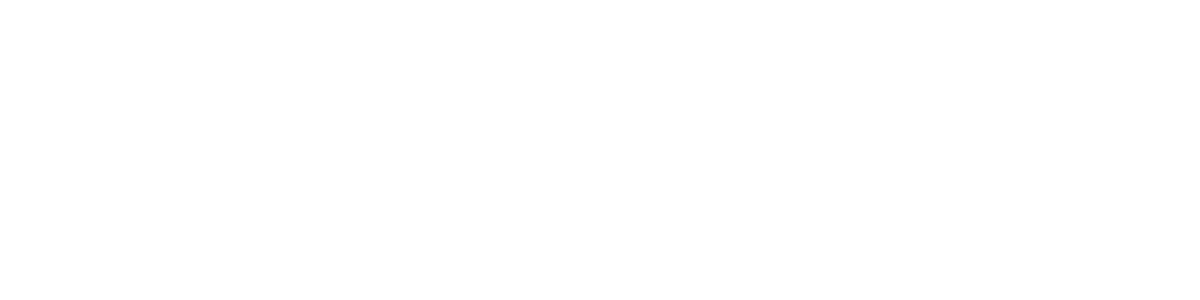
 0
0