maid in …?
2020.12.29
神化論afterの短編です。
▼神化論afterはこちら(画像(バナー)クリックで小説ページへ飛びます)

———————–
「お、お帰りなさいませ、ご主人様!」
そう言って引きつった笑顔を浮かべるのはローズ。
そして彼女の今の格好はというと、やたらフリルが多いデザインの白黒基調の使用人服。
ちなみに使用人とはボーダ大陸の先進国家に多い職業の一つで、上流家庭で住み込みで働く者のことを言う。が、今現在ローズが着ている使用人服は、若干労働には不向きなゴテゴテとフリルやリボンが多い可愛いデザインだった。ついでに黒い猫の耳を模したカチューシャまで頭には付いている。
何故彼女が今こんな格好をして、そしてこんな格好のまま今どこで何をしているかと言えば。
(……仕方ないんだ! コレもお金を手に入れる為!)
そう、全ては金欠から始まった。
◆◆◆◆◆◆◆◆
時は二時間ほど前に遡る。
ジュラードたちはリリンの病の治療法を手に入れに行く途中であり、休憩と道具補充の為に立ち寄ったアサド大陸のとあるオアシスの町の中を歩いていた。
「う~ん……本当にお金が無い……やばい……」
「ローズ、何を不吉な事を言ってるんだ?」
共有財布の中を見ながらブツブツと嫌な事を呟きながら歩くローズに、ジュラードが不安げな様子でそう声をかける。彼の声にローズはハッとした様子で顔を上げ、「だだだ、大丈夫だ!」と蒼白気味な顔色で言った。正直そんな顔色で『大丈夫』と言われても、何も大丈夫な気がしない。
「……そんなにお金が無いのか?」
ジュラードが不安げな顔で問うと、ローズは「大丈夫!」と繰り返す。それを見て、ジュラードは『あぁ、金無いんだなぁ』と理解した。
「でもさぁ、真面目な話、ちょっと今は金欠過ぎよねぇー」
ローズとジュラードの深刻なやり取りに、そうマヤが口を挟む。マヤのこの一言でローズも素直に白状する気になったらしく、「そうなんだよな」と溜息混じりに頷いた。
「旅をするにもお金ってかかるからなぁ……」
「そうだな……」
一応今のジュラードたちの旅の資金は、倒した魔物から素材として売れる部分を調達して町でお金に変えるという方法で確保を行ってはいるが、旅の人数の増加に伴って出費も増えた為に金欠状態となってしまっていた。
「なになに、金ねぇの?」
ジュラードたちが辛気臭い顔で溜息を吐いていると、後ろを歩いていたユーリがそう声をかけてくる。振り返ったローズは、「実はな……」と呟いて頷いた。
「そうか、金無ぇのか」
「困ったね……ご飯食べられない」
ローズがあまりにも深刻な顔をするので、ユーリだけじゃなくアーリィも心配した表情を見せる。ついでにアーリィに抱かれているうさこも、場の雰囲気を察してかしょんぼりした顔で「きゅうぅ~」と力無く鳴いた。
そうして皆が辛気臭いオーラを纏っていると、ちょっと別行動を取っていたイリスとウネが彼らの元へと戻ってくる。こんなチラシを持ってきながら。
「ねぇ見て見て、なんか面白いもの貰っちゃったんだけどね」
そう言いながらウネと共に戻 ってきたイリスは、ジュラードたちに持っていたチラシを見せる。
ユーリがチラシを受け取り、「なんだ?」とそこに書かれている文字を読んだ。
「『使用人喫茶』……なにこれ?」
首を傾げる皆にイリスはこう説明する。
「なんかね、さっきそこですっごい可愛い洋服を着た女の子たちがそのチラシを配っててさぁ。ホントに可愛いから思わず受け取っちゃったんだ。何でも今この辺で、ボーダ大陸の使用人をテーマにした喫茶店がプチブームなんだって」
「? ど、どういうことなんだ?」
さっぱりわけがわからないと言った顔をするローズに、ウネがこう説明を続けた。
「どうやら可愛い使用人服を着た女の子が店員の喫茶店というものが流行っているらしい。お店に行くと男性は『ご主人様』、女性は『お嬢様』と呼ばれて、普通の客とは少し違う扱いを受けるとか。そしてそれが受けていると聞いたわ」
「な、なるほど……」
何となく話を理解したジュラードたちは、『面白いものが流行ってるんだなぁ』という感想をそれぞれに抱く。そんな彼らにイリスが笑いながらこんな事を言った。
「それでさぁ、このチラシのお店って出来たばっかりらしいんだけどね、人少ないから一日でもいいから働いてみないですか~なんて言われちゃってね。ここは男も働けるらしいんだけど、でもさぁ」
イリスは苦笑しながら「給料はそれなりに良かったんだけど、さすがに働くのはね」とウネに同意を求めるように、彼女を見ながら言った。
「そうね、一日働いてくれたら一人三万ジュレ出すと言われたけど、旅をしているし働くのは無理ね」
するとウネのこの一言に、ローズの目付きが変わった。
「一人三万!? と言う事は、皆で働けば……二十四万ジュレ!」
「ねぇローズ、その計算にアタシとうさこ入れてるでしょ? 無理だからね、アタシとうさこは働くの」
マヤの突っ込みも聞いちゃいない様子で、ローズは「働こう!」と力強く言う。
「はぁ? マジかよ、ローズ」
「何か怪しいお店な気がするけど……」
微妙に乗り気じゃないユーリやアーリィの言葉も無視し、お金が無くて胃が痛くなり始めていたローズはチラシに書かれた地図を見ながら歩き始めた。
◆◆◆◆◆◆◆◆
そうして現在に至るわけである。
(うぅ……運良く働けることにはなったけど、これは想像以上に恥ずかしい仕事じゃないか)
正直お金のことしか頭に無かったローズは、真面目にウネの話を聞くといかに仕事内容が恥ずかしいかはわかったはずなのに……と今現在密かに後悔をしていた。
やたら可愛い格好をして、お客様を『ご主人様』と呼んで愛想良く接客しなければいけないなんて恥ずかしすぎる。
そう思いながらローズが大きく溜息を吐くと、傍で物凄いノリノリな様子で働くイリスが通り過ぎた。
「お帰りなさいませ、ご主人様!」
ローズ同様に可愛い系の使用人服を(恥ずかしげも無く)着た彼は、最高の笑顔で入ってきた客を接客し始め る。
「へぇ、君新しく入ったの?」
「名前、何て言うの?」
「イリスです、ご主人様。あのぉ……今日は私のこといっぱい知って満足して帰ってくださいね? 私、ご主人様にならなんでも教えちゃいますし、ご主人様の為ならなんでもしちゃいます」
そう自己紹介をするイリスは、上目使いに男性二人の客を見つめる。客二人はそれだけでデレデレとなり、魔性の悪魔の餌食と化した。
ドン引きしそうなくらいノリノリでかつ可愛いキャラを作って客を魅了するイリスの姿は、なんだかかつての彼を彷彿とさせるなぁとローズは思ったり。いや、むしろパワーアップしてるのかもしれない。
「もしかしてあれも夢魔の力なのか……?」
イリスの接客を見ながら、ローズが若干引きながらも感心した様子でそう呟く。そんな彼女に、彼女の肩に乗っていたマヤが「あれは夢魔は関係ないんじゃない」と冷静に突っ込んだ。
「ユーリが言ってたじゃない、彼は仕事だったら何でもするって。ホント逞しいわよね」
「そうか、それであんな服着ても恥ずかしがらずに……凄いな」
ついに感心が100パーセントに達したローズは、完全に尊敬の眼差しでイリスを見つめる。そんな彼女に、マヤは「お願いだからあなたはアレを目標にしないでね」と言った。
「でもなんで彼は女性の制服を……」
今更それを疑問に思ったローズだが、着てる本人も含めて別に気にしちゃいないようなので、『彼はあれでいいんだな』とも理解した。
「……なんだかイリスは大丈夫そうだな。でも他の皆は……」
そう呟きながらローズが店内を見渡すと、まずは紺色のミニスカートな制服を着たアーリィの姿が目に止まる。アーリィは何か客に料理を運んでいるようで、真剣な表情で料理と共に客の席へ向かっていた。
「……おお、おま、お待たせ……ごしゅじんさま ……」
そう言いながら緊張した面持ちで料理を客の前に置いたアーリィは、一仕事終えた様子でホッと胸を撫で下ろす。ちなみに彼女が運んだ料理はプレーンオムレツで、そこにはケチャップも何もかかっていなかった。
「あれ、このオムレツ……店員さんがメッセージ書いて出してくれるって聞いたんだけど」
オムレツを出された客の男がそうアーリィに聞くと、アーリィは「そうなの?」と首を傾げる。そして数秒考え、何となくそんなことを他の店員に説明されたかもしれないと言う事を薄ぼんやり思い出した。
「……そうだった。メッセージ書き忘れた」
「はははっ、じゃあ今書いてくれればいいよ。書いてくれる?」
お客に言われ、アーリィは頷く。そして彼女は何のためらいも迷いも無く、制服のポケットに入れていた油性マジックを取り出した。
「なんて書けばいい?」
「ちょ、ちょっと待ってメイドさん、何で油性ペン出したの? まさかそれで書く気じゃ……」
青ざめるお客に、アーリィはまた困惑した様子で「ダメなの?」と問う。お客の男は「それじゃなくて、オムレツだからケチャップで書いてほしいな」とアーリィに言った。
「ケチャップ? ケチャップでどうやって?」
「えっと、ほら、チューブのケチャップで……と、とりあえずケチャップもらってきてもらっていい?」
「わかった」
男に言われ、アーリィは素直に頷く。だがアーリィがケチャップを取りに行こうとした直後、チューブに入ったケチャップを片手に執事の格好をしたユーリが彼らの元にやって来た。……物凄い邪悪な笑顔で。
「ご主人様、ケチャップお持ちしました」
「あ、ど、どうも……」
『てめぇ気安く俺のアーリィに近づくんじゃねぇぞ』的なオーラ全開なユーリは、その異様な気配に怯える客に邪悪な笑顔のままでこう言う。
「あぁそうだ、ケチャップにメッセージでしたね。はーい、じゃあ俺が書いてあげますよー」
「え、ちょ、僕はその、彼女に……っ」
予想外にでしゃばってきたユーリに動揺する客などお構い無しに、ユーリは禍々しい笑顔のままチューブを捻ってオムレツの上にケチャップをぶっ掛ける。そしてオムレツの上には、嫌がらせとしか思えない可愛いハートマークが書かれた。
「はーい、俺の愛たっぷりオムレツ完成でーす」
「おぉ、ユーリすごい!」
「あああぁ……僕はそこの彼女に……それを書いてもらいたくて……」
完成してしまったオムレツを前に悲しそうに震える客に、ユーリは止めと言わんばかりに笑顔でこう言う。
「あははっ、泣くほど喜ばれると俺も照れますー。なんならオプションサービスで、俺が『あーん☆』って食わせてあげましょうか?」
「ひっ……!」
スプーンを持って、有無を言わさぬオーラでユーリは客に迫る。
目付きの悪い男(元・暗殺者)にスプーン片手に『あーんして☆』とか殺気全開で迫られたら、それはもう立派なホラーである。
「ほら、口あけてくださいよーご主人様ー。あーん☆」
「う、うわあぁぁ……っ」
こうしてさり気なくアーリィを客に必要以上に近づけさせないよう行動するユーリは、また一人客の心にトラウマを植えつけたのだった。
ユーリが静かに営業妨害するすぐ傍で、ウネもまた猫耳付きの帽子と眼鏡で魔族の容姿をなんとな~く誤魔化しつつ、使用人の服を着て黙々と仕事をしていた。
「パフェ、持ってきたわ」
「あ、ど、どうも……」
ウネは運んできたパフェを、無表情に客の前に置く。それを見ていたジュラードは、ウネが客から離れた後に、彼女に近づいて小声でこう言った。
「なぁ、もう少し愛想良く接客したほうがいいんじゃないか?」
「愛想良く……?」
ジュラードに声をかけられたウネは、怪訝な表情で首を傾げる。ジュラードはそんな彼女に、「接客業なんだし、笑った方がいいんじゃないかと思ったんだが」と言った。
「いや、人相悪い俺が言うのもなんだけど……」
ちなみにジュラードは働き始めて一時間の内に、五回ほど他の店員に『もっと笑顔で接客しろ』と注意されていたり。だがそう指摘されればされるほど、ジュラードの表情は緊張で強張っていき、最後にはもう店員も何も言わなくなってしまったという悲しいオチがある。
ジュラードはこのままだとウネも注意を受けるんじゃないかと心配し、彼女にそう声をかけたのだった。
「笑顔……でも私、正直今機嫌が悪いの」
唐突にそんな事を言ったウネに、ジュラードは「え?」と目を丸くする。するとウネはジュラードにこう言った。
「この服、体にぴったりして窮屈で……イライラする、今すぐ脱ぎたい」
「!?」
ウネの悪癖である”服着たくない”の症状が、彼女の今の機嫌を悪くしているらしい。それを知ったジュラードは、「い、今は我慢しろっ」と慌てた。
「ダメだ、こんな所で脱ぐなっ!」
「わかってる……はぁ、でも脱ぎたい……」
そう言って溜息を吐いたウネに、ジュラードは「が、頑張れ」としか言えない。
「いや、でもやっぱり笑顔は重要だ……少しくらい、笑えないのか?」
「そうね……」
ジュラードに言われ、ウネは憂鬱な気持ちになりながらも無理矢理笑顔を作る努力をしてみる。その結果……。
「……どう?」
「……えっと……」
『どう?』と聞く目の前のウネはどう見ても暗黒面に落ちた黒い笑みで、ジュラードはコメントに困った。無理矢理の笑顔だと、どうも暗黒面に落ちた笑みになってしまうらしい。
「そ、それが笑顔……?」
恐る恐るそうジュラードが問うと、ウネは先ほどのユーリ並に邪悪に笑んだまま頷く。ジュラードは引きつった表情で、「そ、そうか」と頷いた。
「それが笑顔なら仕方ないな……い、いいんじゃないか?」
「そう、これで大丈夫なのね? ……じゃあこれからはこれで仕事する」
「……」
『さっきより悪化したな』と思ったジュラードだったが、もうこれ以上は何も彼女に言う事は出来なかった。
ウネの接客態度を悪化させたジュラードは、彼女をそうしてしまった責任から逃げるように自分の仕事に専念することにする。彼もまた執事の身なりで、主に女性の客を相手に接客することを任されていた。
しかし人付き合いが苦手でコミュ力が限りなく0に近く、その上17年間彼女無しどころか妹一筋で生きてきた彼にとって、妹以外の女性(特に年上)の相手をするなんてのは未知の領域過ぎる話だった。
「お、おお、おかえりなさい、ませ、おじょおさま……」
うさこみたいにガクガクと小刻みに震えながら、ジュラードは棒読み全開でそうやって来た二人組みの女性客に挨拶をする。するとそのジュラードの緊張した態度が逆に受けたのか、成人しているであろう容姿の女性たちは笑顔で彼に近づいた。
「やだ、お兄さん緊張しすぎじゃない? かわいー!」
「新人さん? ちょっと顔怖いけど、でもイイ男ー!」
基本顔は怖いが、しかし整った顔立ちは普通に女性受けする顔なので、幸か不幸かジュラードは女性客に人気である。だが女性に対して免疫の無い彼は、やけに積極的な彼女たちに腕を組まれてどうしたらいいかわからずに気を失いそうになっていた。
と、そんな人気者なジュラードの元に、「きゅいぃ~」と鳴く小さな影が近づく。
「あら、こんなところにゼラチンうさぎ」
「わっ、可愛い! 頭にリボン付けてる~」
両腕をそれぞれの女性の腕と絡め、まさに”両手に花”な状態で失神しかけているジュラードの前に、店側に頭に黒いリボンを付けて”特別店員”として雇って(?)もらっていたうさこが立ちふさがった。
「きゅいぃ~……」
うさこは女性に挟まれたジュラードの姿を見て、何か悲しそうな眼差しで彼を見つめる。その潤んだ眼差しをじっと見つめ、ジュラードはハッとしたように目を見開いた。
「う、うさこ……まさかお前、嫉妬してる……のか……?」
「きゅいぃ~!」
うさこはジュラードの言葉を肯定するかのごとく勢いで、鳴きながら彼に向かって走り、その足に抱きつく。
やっぱりうさこは女の子、なのだろうか……ジュラードを他の女性に取られまいとするそのうさこの態度に、ジュラードはほんの少しだけうさこに対してキュンという胸のときめきを感じ……
「……いや、いやいやいや。冷静になれ俺。こいつはうさこだし。ゼラチンうさぎだし。大体、リリンの方が可愛いし」
危うくうさこに恋しそうになった自分に焦ってアウトなことを口走るシスコンなジュラードに、うさこはやはり鳴きながら彼に必死に引っ付く。
そんな彼の様子を遠くから眺めていたローズは、「ジュラードって人にも魔物にもモテるなぁ」と、のほほんとした笑顔で呟いた。
そしてローズはただ皆を眺めて仕事をさぼっていたのかというとそうではなくて、彼女も一応しっかり働いていた。
「ローズさん、これ5番のテーブルに運んで」
「あ、はい! わかりました!」
ジュラードの様子を眺めてい るとそう声をかけられ、ローズは慌てて食事を運び始める。
「あの、お待たせしましたっ」
初めての接客業に緊張気味のローズは、ぎこちない笑顔でそう言って食事を客の前に出す。男二人組みの客は、そんなローズに「新人さん?」と声をかけた。
「え? あ、はい、ローズって言いますっ」
「ローズちゃん? 可愛いね~」
「黒髪ロングストレートっ娘、萌え~」
「も、もえ?」
ニヤニヤした男たちの発言に首を傾げながらも、ローズは精一杯の笑顔で対応する。そんな彼女を、こっそり服の下でマヤが監視していた。
「ねぇねぇローズちゃん、せっかく猫耳付けてるんだからさ、語尾に『にゃあ』って付けて喋ってよ」
「え、にゃあ !?」
男の一人が突如そんな意味不明な要求をしてきて、ローズはひどく戸惑う。はっきり言って、なんかそれは馬鹿っぽくて恥ずかしい……だけどどうもこの店はそういうのも普通らしく、時々そうやって喋っている店員を見かける。例えばそう、後ろに居る青い髪の毛の店員のように。
「イリスにゃん、はい笑顔でポーズ!」
「にゃ~ん☆ えへ、ご主人様、イリス可愛く撮れたかにゃ?」
「今度は俺と撮ってくれ! イリスちゃーん!」
「はーいですにゃん☆ ご主人様とツーショット、ドキドキしちゃうにゃ」
「……」
ローズの背後で聞えたのは、ワントーン高い声でにゃんにゃんと言う(おぞましい)イリスの声だ。ついでに「うおおぉー!」とか「イリスちゃんーもえー!」とか叫ぶ客の熱気溢れる声も聞える。会話の内容から、撮影機での写真撮影を行っているようだ。
一体あそこで何が起きてるのか後ろを振り向いて確認をしたくなったローズだが、しかしイリスのノリノリの声と盛り上がる客たちの宗教じみた熱気が恐ろしくて振り向けなかった。
(お、俺も彼を見習って……やるべきなのだろうか……)
その圧倒的な適応力と演技力と美貌で着々と信者(という名の被害者)を増やしつつあるイリスを見習い、ローズは『自分も頑張らないと』と覚悟を決める。見習う対象を間違えているような気もするが、とにかくローズは頑張る事にした。
「えと……わ、わかりました……にゃ、にゃん……」
羞恥に顔を真っ赤にしながら、ローズは勇気を出してそう呟く。その恥ずかしそうに『にゃん』と言うローズの姿に、こっちはこっちで男たちも大いに盛り上がった。
「うおおぉー、照れる猫耳っ娘萌えー!」
「ローズたんー! 巨乳猫耳黒髪っ娘で照れ屋さんとかスペック高すぎ、可愛いよーはぁはぁ」
なんかこれはこれで需要があるらしい。
イリスの宗教的なアレとは別の意味で盛り上がった男たちに、ローズは目を丸くして驚き……いや、怯えた。
(なんで盛り上がるんだ……怖いっ)
そして予想外の好感触に涙目で怯えるローズに、男たちはさらにこんなリクエストをする。
「ローズたん、俺たちも一緒に写真撮ろうよ!」
「ひっ、写真…… っ?!」
写真と言えば今現在背後でイリスのイリスによる宗教的な撮影会が行われているが、自分もあんな恥ずかしいことをしないといけないのだろうか……。
本気で怯えるローズに、男たちは「撮ろう!」と押し強く迫った。
「わ、わかりました……」
押しに弱いローズなので、涙目のまま結局頷いてしまう。それが悲劇の始まりだとも知らずに。
「よし、じゃあ撮影コーナーに行こう!」
「ローズたーん」
「……うぅ、どうしてこうなった……」
撮影コーナーの空いている場所で、ローズはガチガチに緊張しながら男たちと肩を並べて立つ。
目の前には撮影機を持った他の店員がいて、撮影機のレンズが自分に向けられると、ローズはますます表情を引きつらせた。
「ダメだよローズちゃん、もっと笑顔でー」
「緊張しちゃうローズたんも可愛いー」
「うぅぅ……」
キリキリ胃が痛くなるのを感じながら、ローズは精一杯笑顔を作ってみようとする。だがどう頑張っても笑顔というより、泣きそうな顔にしかならない。
そんなローズを見かねてか、男たちはこんなことを言った。
「ローズちゃん緊張しすぎ~。もっとリラックスさせてあげるよ~」
「え? ……って、ちょっと……っ!」
男の一人がローズの肩を抱き、さらにあろうことかもう一人の男は腰に手を回す。さらに腰にまわした手をさり気なく下に下ろし……
「ひっ!」
調子に乗った男に尻を撫でられ、ローズは鳥肌を立てる。そしてこのセクハラに、さすがに怒ったローズが抗議しようとした時だった。
「……お姉さま、そろそろアウトですわ。殺っちゃってください」
服の下に隠れていたマヤのドス低い声が聞えた気がした直後、ローズの体は本人の意思を無視して思わぬ行動を取った。
「え……?」
何故か自分の体が勝手に動き、ローズは戸惑いの声を上げる。そして勝手に動いた体は、物凄い重い右ストレートの拳を尻を撫でた男に放った。結果、男はくぐもった悲鳴を上げてノックアウトされる。
「うわああぁー!」
男が倒れ、ローズはわけがわからず動揺に叫ぶ。そして周囲も騒然とし、そこからがローズにとっての本当の地獄の始まりだった。
さらにローズの体は勝手に動き、今度はもう一人の男に向けて華麗な回し蹴りを放つ。いい感じにつま先が下あごにヒットした男は、白目をむいて吹っ飛んで倒れた。
「な、なんで……俺じゃない! 俺は何もしてない! これは体が勝手に……っ!」
騒然とする店内で、ローズはわけがわからずに泣きながらそう叫ぶ。だがその間にも体は勝手に動き、倒れた男の顔をぐりぐりと靴の裏で踏みつけるという鬼な行動を取っていた。
やがて阿鼻叫喚な店内で、ローズはハッと気がつく。
「まさか……ハルファス!」
そうローズが叫んだ直後、ローズの中で『当たりだ』と言うハルファスの声が聞えた。
「ハルファス、何してるんだよ!」
『何って、お前に不埒な真似をする害虫を駆除しただけだぞ。マヤもやれと言ったしな』
マヤの『殺ってしまえ』許可が出たので、ハルファスはローズの体を操って暴走したらしい。さすが最凶のボディーガード、時と場所を考えない暴れっぷりだった。
「だからって、こんなの……」
『まずいだろう』とローズが言い終える前に、彼女は背後に恐ろしい気配を感じて振り返る。そこに立っていたのは……
「て、店長……」
そこには鬼のような形相に無理矢理引きつった笑みを浮かべた 店長の姿が。
そして……
◆◆◆◆◆◆
「結局全員まとめてクビで、給料ももらえないとか……あーもう、馬鹿みたい。私、すっごい頑張ったのに。アホみたく『ニャンニャン』言ってさぁ、馬鹿みたいに盛り上がる野郎共に『ご主人様~☆』とかってタダで愛想と笑顔振りまいたのにさ」
そう愚痴りながら歩くイリスの言葉に心を痛めながら、そのクビの大元凶であるローズが涙目で「すまん」と呟く。そんな彼女をウネが「まぁでも仕方ない」と慰めた。
「そもそも馴れない仕事で稼ごうという発想が間違いだったと思うし」
「俺もそう思う」
「そ、そうだな……」
ウネとジュラードの意見を聞き、ローズは頷きながらも反省した様子で街の中をとぼとぼ歩く。そんな彼女の目の前に、一枚のチラシが差し出された。
「こんにちはー、新しく出来た喫茶店なんですけど、よろしければチラシ受け取ってくださーい」
「喫茶店……?」
何か不吉なものを感じつつ、目の前に差し出されたノリでローズはチラシを受け取ってしまう。そしてそのチラシの隅には、こんな一文が書かれていた。
「『アニマル喫茶、アルバイト急募中……』」
「お、なになにローズ、次はそこでバイトすんの?」
「あら、あなたも懲りないわね。まぁああいう服着たローズは可愛かったけど、男相手にする仕事はもう許さないわよ」
チラシを覗き込むユーリとマヤのそれぞれの言葉を聞き、ローズは引きつった表 情で「もうこういうとこでは絶対働かない」と呟いた。
【END】
NEW POSTED
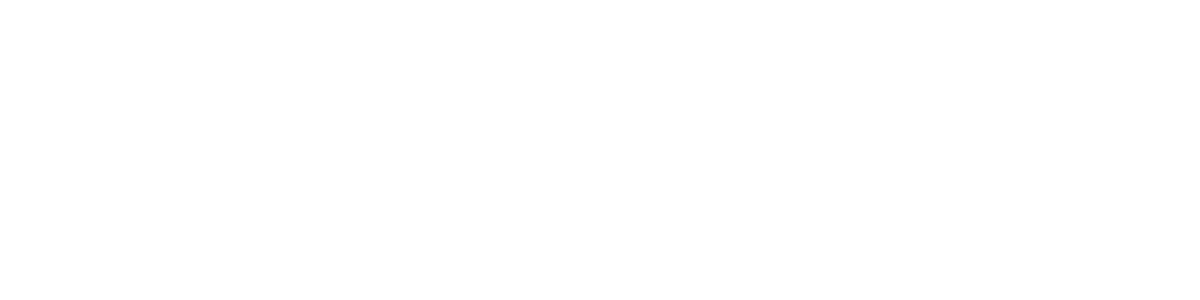
 0
0